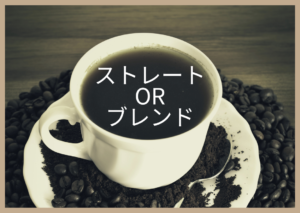【基本】コーヒー焙煎とは?工程ごとに解説【初心者向け】

焙煎とは、コーヒー豆を炒る加熱作業です。
焙煎する前のコーヒー豆は生の状態なので、味も香りもほとんどありません。
コーヒー豆を飲める状態にするには、焙煎を行う必要があります。
焙煎により、コーヒー豆に含まれる成分が変化を起こし、豊かな香りと苦み、酸味、甘味をもったコーヒーが飲めるようになるのです。
今回は、焙煎について基本的な知識から、工程ごとのポイントなどを解説します。
目次
焙煎の基本

焙煎は、生のコーヒー豆を加熱して、香りや成分を適度に生み出すために行います。
焙煎方法はいくつかありますが、熱による変化は同じです。
焙煎の基本をしっかりと理解できれば、さまざまな焙煎機を利用してもすぐに使いこなせるようになります。
生のコーヒー豆は、淡緑色。焙煎すると、淡緑色→茶褐色→黒褐色と変化します。
本記事では、初心者向けにポイントを解説。
以下の5つのポイントをまとめてました。
- 7つの焙煎度
- 焙煎度に適した豆
- 焙煎のやり方
- 温度と火力の調整
- 焙煎時間の影響
それぞれを解説します。
①7つの焙煎度
コーヒーの焙煎には、いくつか段階があり、基本的に大きく分けて3つ、細かく分けると7つのレベルに分類されています。
焙煎度は、コーヒーの苦みや酸味の目安。
それぞれのレベルに適したコーヒー豆もあるので、しっかりと覚えておきましょう。
Point
大きく分けると、浅煎り・中煎り・深煎りの3つに分類されます。
焙煎度は、焙煎の深さによって分類。
本記事では、7つのレベルに分類して解説します。
- シナモンロースト
- ミディアムロースト
- ハイロースト
- シティロースト
- フルシティロースト
- フレンチロースト
- イタリアンロースト
ローストは、焙煎のこと。
シナモン・ミディアムローストは浅煎り、ハイ・シティローストが中煎り、フルシティロースト以上が深煎りに当たります。
浅煎りは、酸味が強く、苦みが弱い風味になります。
深煎りは、苦みが強く、酸味が弱い味わいです。
それぞれの特徴を見てみましょう。
浅煎り

浅煎りは、焙煎時間が短く、酸味が強い特徴です。
苦みはなく、さっぱりした味わいでフルーティーな風味を楽しめます。
【シナモンロースト】
苦みはほとんどなく、スッキリとした酸味。飲みやすい口当たりです。
【ミディアムロースト】
さっぱりした風味に、わずかに苦みのある味わいです。
アメリカンコーヒーに使われる場合が多く、アメリカンローストとも呼ばれます。
中煎り

中煎りは、酸味と苦味のバランスがとれた味わいが特徴です。
浅煎りに比べ、色が暗くしっとりとした豆に。
コーヒー豆本来の風味が出やすいため、レギュラーコーヒーとして世界中で親しまれています。
【ハイロースト】
バランスのとれた味わいで、柔らかい口当たりです。
スッキリとした苦みがおいしいので、迷ったらハイローストを選ぶのがおすすめ。
【シティロースト】
ハイローストに比べ、コクのある苦味が特徴です。
日本や北米で人気の焙煎度で、よりコクのあるコーヒーを味わいたい方はこちらを選びましょう。
深煎り

深煎りは、香ばしい香りとビターな味わいが特徴です。
焙煎時間が長く、豆は濃い茶褐色~黒褐色になります。
酸味が強いコーヒー豆を深煎りにすると、すっきりした味わいに変化。
【フルシティロースト】
コーヒー独特な香りが強く、酸味は少ない風味です。
苦味とコクをしっかりと感じるので、苦いコーヒーが好きな方におすすめ。
【フレンチロースト】
苦みがかなり強く、深いコクが特徴です。
酸味はほとんど感じず、カフェオレやウィンナーコーヒーといったアレンジコーヒーに使われます。
【イタリアンロースト】
独特なスモーキーフレーバーが特徴。
苦味とコクはもっとも強く、ブラックでは飲みずらいと感じる場合もあります。
ミルクやシュガーを入れて楽しむのがおすすめです。
②焙煎度に適した豆
コーヒー豆には、焙煎度に適した豆があります。
さまざまな考え方がありますが、主に地域と標高で分類。
地域による分類
ざっくりとした分類ですが、主に世界を4つの地域に分けて考えます。
- アジア…深煎り
- 中米…浅煎り
- 南米…中煎り
- アフリカ…浅煎り〜深煎り
国や生産国によっても異なるので、あくまで参考程度に考えましょう。
例えば、年米でも浅煎りに向いたコーヒー豆もあります。
標高による分類
生産地の標高によって分類する方法です。
コーヒー豆は、標高によって重いコーヒー豆ができる傾向にあるため、深煎りに向いていると言われています。
硬くて重い豆は、深煎りしても形が苦味がでないためです。
ただし、こちらもあくまで参考程度。
低地が産地のコーヒー豆でも深煎りに適した豆はたくさんあります。
実際の適した焙煎度を把握するには、実際に焙煎するのが一番です。
③焙煎のやり方
ここからは、基本的な焙煎のやり方を解説します。
焙煎の構成は以下の通りです。
- 水抜き
- 1ハゼ
- 2ハゼ
- 冷やす
水抜き後、焙煎が始まり、加熱時間によって焙煎度が変化するイメージ。
Point
ハゼとは、加熱によって豆が「パチっ!」と弾ける現象です。パチッと1回弾けたら、1ハジとカウントします。
それぞれ解説します。
①水抜き
コーヒー豆を焙煎する際は、コーヒー豆を蒸らして、水分を抜きましょう。
水抜きは、焙煎する豆の量に関わらず、5分を目安に蒸らすのがおすすめ。
水抜きの時間は、多少多くなっても問題ありません。
ただし、水抜きが十分でないと、風味が悪くなり、ムラの原因になるので注意が必要です。
②1ハゼ
水抜きが終わったら、いよいよ焙煎スタートです。
コーヒー豆を加熱し、焙煎を進めていきましょう。
数分間焙煎すると、コーヒー豆が膨らみ、パチっと爆ぜる音が聞こえてきます。
焙煎する量や火加減にもよりますが、約2~3分で1ハゼが終了。
ハゼが始まった時点で焼き上げるとシナモンローストに、1ハゼが終了した時点ならミディアムローストになります。
また、次の2ハゼまでの間に焼き上げれば、ハイローストです。
③2ハゼ
1ハゼ終了後、約1~2分で2ハゼが始まります。
2ハゼが始まった時点で焼き上げれば、シティローストです。
2ハゼは、1ハゼよりもバチバチと強い音が特徴です。
加熱による変化も大きので、秒単位で風味が変わります。
2ハゼピークで焼き上げると、フルシティロースト。
2ハゼ後半ではフレンチロースト、2ハゼ終了間近でイタリアンローストです。
④冷やす
焼き上げたコーヒー豆は直ぐに冷やしましょう。
すぐに冷やさないと、コーヒー豆の熱で焙煎が進んでしまいます。
ただし、水に入れるのは厳禁。
フライパン焙煎や冷却機能のない焙煎機なら、ドライヤーの冷風を使いましょう。
風を当てると、チャフと呼ばれる薄皮が飛び散るので注意。
人肌まで冷やしたら焙煎は完了です。
Point
焙煎では、コーヒー豆の色の変化よりも、ハゼの音で焙煎度を把握します。
④温度と火力の調整
焙煎では、火力も重要です。
火力は強すぎても、弱すぎても上手くいきません。
とくに、初心者にとっては最初のハードルと言えます。
火力はコーヒー豆の量によって調整
コーヒー豆の量によっても、適切な火力は異なります。
焙煎では「コーヒー豆の量に関わらず、焙煎時間を一定にするのが理想」です。
かんたんに言えば、コーヒー豆の量が倍なら、火力も倍にするイメージ。
焙煎は中点を一定に
焙煎では、中点という考え方があります。
中点は、焙煎機に冷たいコーヒー豆を投入し、焙煎機内の温度が下がり切ったポイントです。
中点に達した温度は、加熱によりすぐに上昇に転じます。
中点は、一定にするのが望ましいです。
事前に焙煎機を温めておき、中点をコントロールします。
ただし、手回し焙煎機を使用する場合では、中点を気にしなくても問題ありません。
⑤焙煎時間の影響
焙煎時間に正解はありません。
コーヒー豆の種類や求める風味によって、ちょうど良い焙煎時間を探しましょう。
焙煎時間の長さには、メリットデメリットがあります。
焙煎時間が短い
焙煎時間が短い場合、風味や香りが強いメリットがあります。
一方、ムラが出やすく、雑味がまじりやすくなる点はデメリットです。
焙煎が短いと、成分があまり飛ばないので、風味や香りが強くなります。
短時間で強い熱を加えるので、豆が傷みやすく保存に悪影響がでるケースも。
焙煎時間が長い
焙煎時間が長い場合、ムラがなく、クリアな風味になります。
一方、風味や香りが薄いデメリットも。
成分が飛んでしまいますが、ムラなく焼けるのでクリアな風味になります。
また、保存状態がよくなるケースも。
Point
温度を抑えて長時間焙煎するとクリーンな風味になりますが、やり過ぎると内部が焦げる可能性があるので注意です。
焙煎も豆選びが重要

これまで、焙煎の基本やポイントを解説しました。
しかし、焙煎においても重要なのは豆選びです。
自分好みの風味を味わいためには、あったコーヒー豆を選びましょう。
品質の良し悪しも、風味に大きく影響します。
品質のよいコーヒー豆は、焙煎が雑でも旨味のあるコーヒーに仕上がります。
ただし、品質を図る基準がないのもポイント。
価格やグレードなどを重視しがちですが、安くても美味しいコーヒーはたくさんあります。
ぜひ、自分自身の舌で、質のよいコーヒーを見つけてみましょう。
焙煎の基本をおさえておいしいコーヒーを
焙煎は、生のコーヒー豆を加熱して、香りや成分を適度に生み出すために行います。
焙煎には、これといった正解はありませんが、基本的なポイントをおさえて自分にあった焙煎度や時間をみつけましょう。
豆の種類、銘柄、火の温度によって風味は変化するので、試行錯誤をして風味を探していくのがおすすめです。
ぜひ、楽しみながらさまざまな工夫を試してみください。
投稿者プロフィール
-
コーヒー歴10年以上。コーヒーと紅茶を愛するwebライター。
喫茶店が大好きで、新しい味わいとデザインに出会うために日本中を旅しています。
webマーケティングやwebデザインも手掛ける。最近の趣味はインドアガーデニング。
最新の投稿
 Office2023.02.26【第1回】ビジネス×デザイン|ビジネスにおけるデザインの重要性
Office2023.02.26【第1回】ビジネス×デザイン|ビジネスにおけるデザインの重要性 Gardening2023.02.26【入門】基本用土 赤玉土とは?特徴・成分・効果について【配合方法も解説】
Gardening2023.02.26【入門】基本用土 赤玉土とは?特徴・成分・効果について【配合方法も解説】 Gardening2023.02.24【入門】基本用土 黒土とは?特徴・成分・効果について【配合方法も解説】
Gardening2023.02.24【入門】基本用土 黒土とは?特徴・成分・効果について【配合方法も解説】 Food2023.02.23【基本】ロブスタ種とは?コーヒーの原種について【特徴・違い】
Food2023.02.23【基本】ロブスタ種とは?コーヒーの原種について【特徴・違い】